普段生活をしているとテレビや雑誌などで
今急成長中のIT企業社長の年商はなんと100億円・・・
個人で始めたパン屋さんは商品がヒットして
大行列で年商が3億円になった社長!などなど。
やたらと年商というワードを使われる事は多くあります。
特にテレビや雑誌などのメディアが年商という言葉を
よく使っているので、年商という言葉は事業をしていない人でも
耳にする機会は多いのではないでしょうか。
では、実際に年商とはどういった意味なのでしょうか?
私自身は会社員をしてから起業をして現在に至りますが、
いつの間にか自然と年商の意味は知っていました。
この記事では、会社に入ってくるお金についての呼び方として
売上高と年商は同じなのか、利益は年商とどういった点が
違うのかなどについて解説します。
会社員から経営者までビジネスをしている人や
興味がある人にとっては基本的な知識なので
しっかりと押さえておくといいですね。
年商とは何?
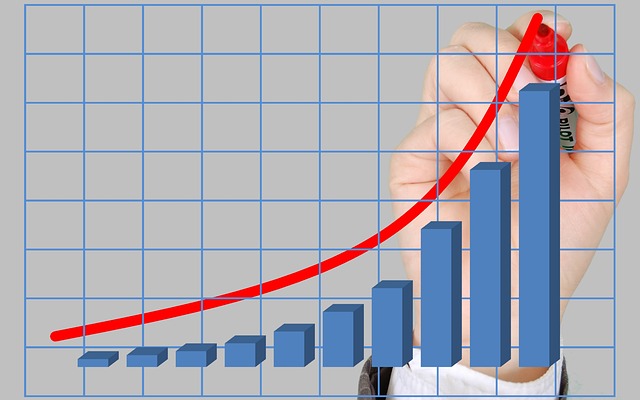
年商という言葉については、簡単に表現すると、
会社や個人事業主などの「年間の売上の合計金額」のことを意味します
例を出してみると、ネットショップで通販サイトを運営していたとします。
洋服が1日に50着売れて、
売上が20万円だったとしましょう。
この場合には「日商」で20万円。
このまま同じ金額で30日間の間ずっと同じ売上が
続くと「月商」600万円。
年商=600万円×12カ月=「年商」7200万円ということになります。
つまり年商という表現は会社や個人事業主が
ビジネスによって生み出した単純な売上のみ。
業種によって高い商品やサービスを
提供していると年商の金額がとても高くなるという事もあります。
例えば、会社や個人事業主を相手にした事業をしていて、
1つ販売すれば数百万円や数千万円のようなビジネスもあります。
個人相手のビジネスでも不動産の販売なんて
1棟や1部屋で何千万円や何億円の事業ですよね。
ただし、実際に重要になるのはその売上の中でどのくらいの
お金が残るものなのかどうかという点ですよね。
こういった点から考えると年商というのは年間の売上だけなので、
金額として一番高く見せれるので広告として目を引くことが出来るので
テレビや雑誌などで多用される理由になっています。
売上高とは?

売上高とは、一定期間で法人や個人事業主などが
商品やサービスなどを販売したことによって得る事が
できた売上の合計額を表します。
つまり、月商や年商のように期間を区切っていないので
売上高という表現だけの場合にはどこからどこまでの期間の売上高なのか
知ることができないという事になります。
そのため、誰かが売上高はいくらですと言ったり、書類に書いていても、
いつからいつまでの売上高なのかを確認できない限り事業状況は
分からないということになります。
例えば、大きな企業の場合には、
5年間の売上高の推移などを公開していて、過去5年の売上高は~
という表現をすることがあります。
5年間の売上高の推移など、このような会社の財務情報では、
1年ずつの年間の売上高を投資家向けに公開しています。
こうやって売上高については期間がいつからいつまでのものなのか知る事で、
一定期間でどのくらいの売上高を出している企業なのかがわかります。
年商と売上高の違いについて

上記でも書いたとおり、
年商は1年間で出す事ができた売上の合計金額を表しています。
売上高については売上を意味するという部分は同じです。
売上高の場合に大きく違うのが期間の区切りがないという部分で
これまでの期間において、どのくらいの売上を出したのかを意味します。
それは、つまり期間を区切っていくと
年商などと同じ意味になるということなのです。
そのため、1年間の売上高については年商を意味します。
期間を区切ってしまえば、年商と売上高は同じということですね。
月商については一カ月の売上高、
日商については1日の売上高と同じ意味です。
利益とは何?
利益とはなんなのかというと売上高のように
会社などに入ってきた全てのお金を意味するわけではありません。
簡単にいうと、売上を生み出すためにかかった経費や
その他の様々なものを足したり、引いたりして残ったお金を意味します。
仕入れや製造に使った費用を引いたり
物を販売するための場所として、借りていた不動産賃貸料や
水道光熱費から通信費などなど。
様々な経費を差し引いた上でさらに本業の業務以外で
受け取った利益や損失などもすべて計算した上で最終的に税金なども
すべて支払った後に残るのが純利益というものです。
つまり、純粋な儲けの部分ということになります。
純利益が多い会社というのは、税金もたくさん払っている上で
利益が残っているのでかなり儲かっていると言えます。
ただし、こちらは事業規模によっても変わりまして、
個人事業主や小規模の会社であれば、節税をしていて利益は少ないけど
経済状況がとても良いという場合も多いです。
純利益として残るお金は少ないけど、
かなり余裕のある生活をしている事業者はたくさんいます。
年商が高い人でも、経費が多い場合や何らかの損失があれば、
利益は少ないもしくは赤字という経営者は多いということです。
目先の利益も大切な事ですが残る金額を設備投資や未来の利益に
繋がるようなものにお金を投資したり、いざという時のためにお金を残すなどのバランスが大切です。
人件費での給与や製造や仕入れにかかった費用などだけで
利益がなく赤字という状態の場合にはお金を少しでも残していけるように考えるべきです。
年商が1億円や5億円や100億円は凄いの?
冒頭でも書いた通り、年商をド派手に広告に掲載しているネット広告や
社長の出演する番組では年商という言葉を使うというパターンは多いです。
年商という言葉を使って宣伝をする事が
一番金額的にインパクトがあるので、年商という言葉を使っているという事になります。
この社長は純利益がいくらです。と表現すると経費や税金などが引かれた
金額なので全然大きな金額にならない人がほとんどです。
もちろん、どのぐらいの金額から
インパクトを感じるのかは人それぞれですが。
年商は1年を通しての売上のみの金額なので大きな金額になります。
そのため、インパクトがあるので凄そうな感じがするという事です。
年商という言葉だけでは何億円であっても凄いかどうかわからないです。
年商100億円の会社でも赤字で倒産寸前のような会社もありますからね。
年商1億円であっても原価などがほとんどかからずに
人件費も少なくて済んで、広告費もかからないような
事業だと利益はかなり残るでしょう。
あくまで例ですが、IT系やコンサルティングの仕事などは特に経費が少なくて
少人数や一人事業であっても大きな利益を生み出せる職業といえます。
このような例の場合には、年商100億円の人よりも年商1億円の社長の方が
金銭的、精神的なゆとりは多そうで凄いなと思う人も多いのではないでしょうか。
年商という表示や広告には気をつけよう

年商というワードについては、大きな金額を見せることで、
インパクトを出して興味を引いたりする為などに使われることが分かりました。
ビジネス上で取引をしようと思っている会社の
年商が高いからといって安心なのではなく実際の経営状況を
見ることを意識するように気をつける方がいいでしょう。
利益が残っていなくて、なおかつ現金以外でお金を残すような
ことができていない状態で赤字になっている状態であれば
全然安定した経営とは言えませんからね。
まとめ:
今回の記事では年商とはどんな意味を表しているのかという
部分を中心に売上高との違いなどについて紹介しました。
年商という言葉が一番誇大に見せれるものとして
テレビや雑誌等のメディアで広告戦略として使われていることが分かりました。
年商1億でかなり余裕のある経営者もいれば
年商で10億円を超えているけど、経営危機に陥っているという
会社も普通にあるということです。

コメント